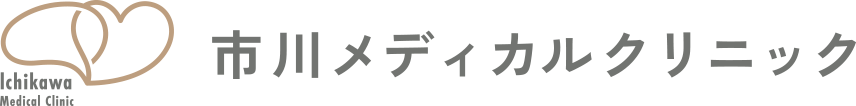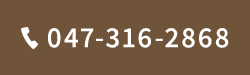炭酸リチウムと攻撃性・暴力行動への治療効果
炭酸リチウム(リーマス)は主に双極性障害の治療薬(気分安定薬)として知られていますが、近年までの研究で攻撃性や衝動的な暴力行動を低減する効果が一般集団においても示唆されています。この抗攻撃性効果は動物実験から人間の様々な集団まで一貫して報告されており、例えば高齢者施設の入居者、知的障害のある患者、衝動的で攻撃的な子ども・青年、さらには刑務所の受刑者に至るまでリチウム投与による攻撃行動の減少が観察されています。モラルハラスメント(モラハラ)やドメスティックバイオレンス(DV)は対人場面での攻撃的行動や情緒コントロールの問題として位置付けられるため、双極性障害ではない一般の人々においても、リチウムがそうした攻撃性を抑え感情コントロールを改善するかが注目されています。
子ども・青年における攻撃行動への効果
双極性障害ではない若年層に対する研究として、行為障害(素行障害)を持つ子ども・青年の深刻な攻撃行動にリチウムが有効か検証した無作為化比較試験があります。入院治療を要する重度の攻撃性を示す少年少女を対象に4週間の二重盲検試験を行ったところ、リチウム投与群では攻撃行動の指標(オーバート・アグレッション・スケール)がプラセボ群より有意に低下しました。この研究では、臨床的に著明な改善が認められた被験者の割合もリチウム群(20人中16人)でプラセボ群(20人中6人)より有意に高く、著しい攻撃性を伴う児童・思春期患者に対してリチウムが短期的に安全で有効な治療となり得ることが示されています。同様の傾向は1990年代の複数の研究でも報告されており、リチウム投与中は多動・敵対的行動や衝動的攻撃性が軽減する例があるものの、一部の試験では効果が限定的であったとの結果も見られます。しかし総じて、攻撃的行動の激しい子どもや青年においてリチウムが攻撃性や感情の高ぶりを抑える効果が確認されています(※特に感情的に爆発しやすいタイプの攻撃性に効果が高い可能性が示唆されています)。
成人・人格障害者に対する効果
双極性障害ではない成人に対する研究としては、慢性的な精神疾患や人格傾向に問題を抱える患者にリチウムを用いた事例があります。たとえばVan PuttenとSandersによる初期の研究(1975年)では、双極性障害ではない慢性精神疾患患者35名にリチウム長期投与を行い、治療中に攻撃的行動が著しく改善したと報告されています。またRifkinらの古典的研究(1972年)では、感情的に不安定で攻撃衝動のある人格障害患者を対象に6週間の二重盲検クロスオーバー試験が実施され、リチウム投与群で顕著な攻撃性の低下(情緒安定の改善)が認められたとされています。著者らはこの劇的な改善について、被験者に潜在的な双極性気質があった可能性にも言及していますが、少なくとも双極性障害と診断されていない成人でもリチウムが衝動的攻撃行動を減少させうることを示した重要な結果です。
犯罪者・受刑者における攻撃性への影響
反社会的行動や暴力犯罪歴のある人々に対しても、炭酸リチウムの攻撃性抑制効果が繰り返し検証されています。1970年代には複数の「受刑者スタディ」が行われ、刑務所内で暴力的・衝動的な受刑者にリチウムを投与すると攻撃的感情が和らぎ、懲罰が必要な違反行為の発生が減少することが示されました。例えばSheardらによる最初期のプラセボ対照研究(1970–71年)では、リチウム投与群の受刑者は自ら報告する攻撃的感情が減少し、刑務所内で懲戒処分となる事件の発生率も低下しています。続くTupinらの長期試験(1973年)でもこの抗攻撃効果は再現され、暴力的な受刑者たちはリチウム服用中「怒りの感情を抑えやすくなり、行動の結果を考えられるようになった」と自己報告しています。さらにSheardらは中等度警備刑務所の受刑者66名を対象に3か月間の二重盲検試験を行い、リチウム群で重大な規律違反(暴力事件など)の発生数がプラセボ群より有意に少ないことを明らかにしました。これらの知見は、双極性障害の有無にかかわらずリチウムが人間の衝動的攻撃行動を抑制し得る有力なエビデンスとなっています。
家庭内暴力・虐待に対する効果
モラハラやDVそのものに直接言及した臨床研究は多くありませんが、家庭内暴力の一例として児童虐待へのリチウムの効果が報告されています。ブラジルの研究者Prado-Limaらは、実子に虐待的な暴力行為を行っていた母親8名を対象にオープンラベル試験を行い、リチウム投与前後で虐待行動の変化を評価しました。その結果、リチウム服用開始から30日後および60日後に、母親たちの児童虐待行動(主に身体的虐待)がベースラインと比べて有意に減少し、特に「他者(子供)に対する身体的攻撃性」のスコアが著明に改善したことが報告されています。この予備的報告は症例数こそ限られますが、親による家庭内暴力をリチウムで軽減できる可能性を示す興味深い知見です。なお、配偶者間のDV加害者に対する直接的な介入研究は2025年現在見当たりません。しかし上述のように、リチウムには衝動性や易怒性を抑えて攻撃行動を減らす作用が確認されているため、感情のコントロール困難から生じる対人暴力(言葉の暴力を含む)に対してリチウムが有効となる可能性が示唆されます。実際、リチウム投与によってパートナーや家族が被る精神的・身体的な苦痛の軽減につながったケースがあることから(児童虐待の改善例など)、モラハラ・DV行動の是正手段としてさらなる研究が期待されます。
一般集団レベルでの観察所見
炭酸リチウムの攻撃性低減効果は、医薬品としての直接投与だけでなく環境中の微量リチウムと暴力傾向の関係からも示唆されています。近年の生態学的研究では、地域の水道水中に含まれる天然のリチウム濃度がその地域社会の暴力犯罪率と関連することが報告されました。例えば日本の九州地方274自治体を対象にした横断研究では、水中リチウム濃度と暴力犯罪発生率との間に有意な逆相関が見られ、リチウム濃度がわずかに高い地域ほど犯罪率が低い傾向が示されています。著者らは「ごく低濃度のリチウム曝露であっても一般集団における暴力的犯罪行動の抑制に寄与している可能性がある」と結論付けており、リチウムを微量添加した飲料水の摂取など公衆衛生的介入によって自殺や暴力犯罪を予防できるのではないかという提案も議論されています。実際、アメリカや欧州の一部地域についても、水中のリチウム濃度が殺人や強盗など暴力犯罪率の低さと関連するとの報告があり、この関連は世界的にも注目を集めています。
まとめ
炭酸リチウムは双極性障害以外の一般集団においても、攻撃性の低下や感情コントロールの改善に寄与しうることが複数の英語査読付き研究から示されています。特に、反抗的・衝動的な若年層や人格傾向に問題のある成人、暴力的な受刑者といった幅広い対象でリチウム投与による対人攻撃行動の抑制効果が確認されています。家庭内暴力という観点でも、少数例ながらリチウムによって親による虐待行為が減少した報告がありd-nb.info、モラハラ・DV的な行動を含む対人暴力の是正にリチウムが役立つ可能性が示唆されます。これらの研究知見は、モラハラやDV加害行動の背景に感情制御の障害や衝動性が関与している場合に、炭酸リチウムがその改善に寄与しうることを示すものです。ただし、リチウムは治療域と中毒域が近く副作用管理が重要な薬剤でもあるため、DV行動の薬物介入として用いるには慎重な検討が必要です。今後、モラハラ・DVを含む対人暴力の低減策としてリチウムを評価するさらなる臨床研究が望まれています。
参考文献