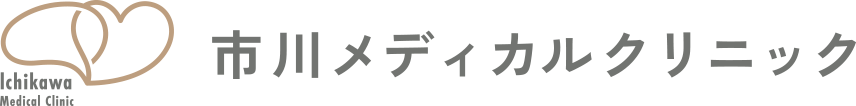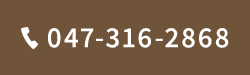炭酸リチウムの認知症予防効果に関する最新情報
背景
炭酸リチウム(リーマス)は古くから双極性障害の治療薬として用いられてきましたが、近年、その神経保護作用に注目が集まり、アルツハイマー病(AD)など認知症の予防・進行抑制への可能性が検討されています。リチウムは細胞内シグナル伝達系への多面的作用を持ち、アミロイドβ(Aβ)蓄積抑制やタウ蛋白の過剰リン酸化抑制、炎症反応の制御、神経栄養因子の増加など、多岐にわたる効果が示唆されています。本記事では、炭酸リチウムの認知症予防効果に関する人を対象とした研究知見を、疫学研究、臨床試験、神経生物学的メカニズムの観点から総合的に概説します。

疫学研究における認知症予防効果のエビデンス
双極性障害患者を対象とした観察研究では、長期リチウム療法を受けた群で認知症の発症リスク低下が複数報告されています。例えばデンマーク全国データを用いたKessingらの研究では、リチウム処方歴のある双極性障害患者は処方歴のない患者に比べ認知症発症が少ない傾向が示されました。一方でDunnら(2005年)の報告では明確な予防効果は確認されず、初期の研究間で結果が一致しない点も指摘されています。しかし、近年発表された大規模研究の知見はリチウムの予防的関連を強く支持しています。Chenら(2022年)は英国の約15年間の後ろ向きコホートデータを解析し、リチウム投与群(平均血中濃度0.61 mmol/L)では非投与群に比べ認知症発症ハザード比(HR)が0.56と有意に低下していました。アルツハイマー型認知症に限ればHR 0.55、血管性認知症ではHR 0.36と、それぞれ統計的に有意なリスク低下が示されています。さらに同研究では、リチウム曝露期間が短期(1年以内)および長期(5年以上)の場合に予防効果が顕著で、中期(1~5年)ではサンプル数の不足により有意差が見られないものの、曝露期間に応じたリスク低減の傾向が示唆されました。実際、リチウム曝露期間と認知症発症リスクには線形的な負の相関が示唆され、使用期間が長いほど全認知症およびADのリスクが低減する可能性が報告されています。また、リチウム処方回数に着目した解析では、処方回数が複数回(5~19回)の患者は1回のみの患者より認知症リスクが低いとの知見もあり、累積投与量による効果の存在が示されています。これら疫学データは、リチウムの服薬歴が認知症発症の抑制と関連することを示唆します。
一般集団における研究としては、地域の水道水中の微量リチウムと認知症発症率の関連を調べた研究があります。デンマーク全国の地質学的データと医療記録を突合した研究では、水中リチウム濃度が高い地域ほど認知症発症率が低いという逆相関関係が報告されました。テキサス州でも地域の水リチウム濃度がADによる死亡率低下と関連するとの報告があります。一方、米国で行われたParkerらの解析では、リチウム濃度と認知症有病率に表面的な逆相関が見られたものの、地域の年齢構成や医療アクセス等の交絡因子を統計調整すると関連は消失し、水中の微量リチウム自体が予防効果をもたらす明確な証拠は得られませんでした。この結果は地域差の要因を精密に調整する重要性を示しています。さらに日本における全国疫学研究では、水道水リチウム濃度が高い地域の女性高齢者でAD有病率が有意に低いことが報告されており、性別による効果差も示唆されています。このように、水中リチウム濃度と認知症リスクの関連については国や研究デザインによって結果が分かれているものの、概ね高リチウム曝露が認知症リスク低下に結びつく可能性が示唆されています。地域水準での微量リチウム曝露効果は個人レベルの交絡因子の影響を受けやすいため、今後さらなる検証が必要です。
臨床試験とメタアナリシスの結果
リチウムの認知症領域への効果を直接検証するため、軽度認知障害(MCI)やAD患者を対象にランダム化比較試験(RCT)が実施されています。症例数は比較的小規模ながら、認知機能の低下抑制効果を示す結果が蓄積してきました。Forlenzaらは記憶障害型MCI患者を対象に2年間の低用量リチウム投与RCTを行い、プラセボ群に比べリチウム群で認知機能および日常機能の維持が確認されたと報告しています。具体的には、プラセボ群では2年間でADAS-cogやCDR-SBスコアの悪化が認められたのに対し、リチウム群では認知機能スコアが安定しており、特に記憶や注意力の測定で有意に良好な成績を示しました。加えて、生物学的指標として脳脊髄液中のAβ_1-42濃度を経時的に測定したところ、リチウム群では36か月時点でAβ_1-42が有意に増加しており、これはADで低下するAβ_1-42の維持・増加すなわち病的アミロイド蓄積の抑制を示唆する所見です。結論として著者らは、「長期の低用量リチウム投与によりMCI患者の認知機能低下と機能喪失が抑制され、AD関連のバイオマーカーが改善する」と述べ、リチウムの疾患修飾的効果(disease-modifying effect)の可能性を示唆しました。この試験は当初15か月時点での中間解析結果も報告されており、早期からタウ蛋白リン酸化抑制効果や認知機能悪化抑制の兆候が見られていたことが後のメタ分析にも組み込まれています。他にも、軽度~中等度AD患者を対象とした短期間のRCTがいくつか実施されており、認知機能への明確な有意差は得られなくともCSF中タウ蛋白の減少など病理マーカーへの作用が報告された例があります。これら単独の試験規模は小さいものの、同方向の効果を示す傾向が見られています。
複数のRCT結果を統合してリチウム効果を評価したメタアナリシスも実施されています。Matsunagaら(2015年)の系統的レビュー・メタ解析では、ADまたはMCI患者を対象としたランダム化プラセボ対照試験3件(総症例232例)のデータが統合されました。解析の結果、リチウム投与群はプラセボ群より認知機能悪化が有意に小さいことが示され、標準化平均差(SMD)は-0.41(95%信頼区間 -0.81~-0.02)と有意差が得られました。これはリチウム群の方が相対的に認知機能が保たれていたことを示します。ただし、AD患者のみ、MCI患者のみでサブグループ解析を行うと、それぞれ単独では統計的有意には達しなかった(MCI:p=0.59、AD:p=0.07)ことも報告されています。症例数の限界から明確な結論は難しいものの、全体としては小規模ながら臨床的有益性を示す傾向が支持されました。さらに近年、観察研究も含めリチウム療法と認知症リスクの関連を包括的に評価したメタアナリシスが発表されつつあります。Luら(2024年)は最新のメタ解析で、リチウム療法が認知症全般の発症リスク低下およびAD有病率の減少と関連する可能性を示しており、エビデンスの蓄積が進んでいます。総じて、リチウムの認知症進行抑制効果を示す臨床研究は徐々に増えており、その有効性を支持する証拠が強まりつつあります。ただし、大規模で長期間のRCTは未だ不足しており、決定的な結論には更なる検証が必要です。
炭酸リチウムの臨床応用の可能性と課題
上述の知見を踏まえ、炭酸リチウムを認知症予防または進行抑制の目的で臨床応用する可能性が議論されています。特に双極性障害患者やMCI患者において認知症発症リスク低減が示唆されたことから、高リスク群に対する予防的リチウム投与という概念が浮上しています。一方で、リチウムは治療域が狭く高用量では中毒の危険がある薬剤であり、臨床応用には慎重な検討が必要です。双極性障害の維持療法で用いられるリチウム血中濃度0.6~1.0 mmol/L程度の標準用量でも、有効性とともに腎機能低下や甲状腺機能低下などの副作用リスクを伴います。そのため、認知症予防目的ではより低用量での長期投与が現実的と考えられます。実際、前述のForlenzaらのRCTでは0.25~0.5 mEq/Lというサブセラピューティック(治療域下限)濃度を目標とした低用量で効果が認められました。また、他の研究でも1日あたり数mg程度という微量のリチウム(通常の治療量は数百mg)で認知機能の安定化を報告した例があり、微量リチウム補給による安全な予防的介入の可能性が示唆されています。水道水中の微量リチウム濃度差で長期的リスクに差が生じるとの疫学知見も、ごく低用量であっても持続的な曝露が効果を持ちうることを示す点で示唆的です。
臨床応用にあたっては用量反応関係や投与期間の最適化が重要な検討課題です。現在得られているデータからは、一定期間以上の継続投与が効果発現に必要である可能性があります。Chenらのコホート研究では1年以上のリチウム服用で効果が示され、特に5年を超える長期では有意なリスク低下が認められました。逆に1年未満の短期使用でも効果が示唆されましたが、これは双極性障害のエピソード治療などで断続的に用いた場合でも累積効果があるのか、あるいは偶然か議論の余地があります。少なくとも長期連続投与を躊躇させる要因として、副作用管理の問題があります。リチウムは血中濃度モニタリングが不可欠な薬剤であり、高齢者では腎排泄能低下に伴う中毒リスクも考慮しなければなりません。したがって、予防的に用いる場合には低用量で安全域を保ちながら定期的な血中濃度・臓器機能モニターを行う必要があります。また、現時点で認知症発症予防を適応としたリチウム処方は標準医療には含まれておらず、保険適用上の課題もあります。臨床試験的な位置づけで、特にリスクの高い集団(例:家族性ADの前臨床期やMCI患者、双極性障害高齢患者など)に対し慎重に検討される段階です。今後、大規模プラセボ対照試験によって有効性と安全性のバランスが確認されれば、予防的リチウム療法が現実の選択肢となる可能性があります。しかし高齢者集団を対象に長期追跡する試験は費用・倫理両面でハードルが高く、現実にはエビデンス集積に時間を要することも指摘されています。患者ごとのリスク・ベネフィットを評価しつつ、臨床応用への最適戦略(対象、時期、用量、投与形態)の検討が求められています。
認知症のサブタイプについて
近年の疫学研究と臨床試験から、炭酸リチウムは特にアルツハイマー型認知症(AD)と血管性認知症(VD)の発症リスクを下げ得ることが示唆されています。英国の約3 万例を12 年間追跡したコホートでは、リチウム使用者でADのハザード比が0.55、VDは0.36に低下しました。さらに、軽度認知障害や早期ADを対象とした無作為化比較試験では、0.2–0.5 mmol/L程度の低用量リチウムを12〜15 か月投与することで認知機能低下と髄液リン酸化タウの上昇が抑制されることが報告され。メタアナリシスでも同様の傾向が支持されており、予防薬候補としての位置づけが強まりつつあります。一方、レビー小体型認知症(DLB)や前頭側頭型認知症(FTD)に関しては臨床データが乏しく、現時点で有効性は未確認です。総じて、炭酸リチウムはADを中心に発症予防の可能性が高い一方、他の認知症タイプでは今後の検証が不可欠といえます。
神経生物学的メカニズム
炭酸リチウムが示す認知症予防効果の背景には、複数の神経生物学的メカニズムが関与していると考えられます。主要な作用標的の一つがグリコーゲン合成酵素キナーゼ3β(GSK-3β)の阻害です。GSK-3βは脳内でタウ蛋白のリン酸化促進やAβ産生亢進に関与する酵素で、AD病態形成に深く関与しています。リチウムはこの酵素の活性を直接・間接に抑制し、タウの過剰リン酸化を抑制して神経原線維変化の形成を減少させるとともに、Wnt/β-カテニン経路の調節を介して神経細胞生存に有利な遺伝子発現を促します。具体的には、リチウムによるGSK-3β阻害によりβ-カテニンの分解が抑制され、核内に移行したβ-カテニンがBACE1(βセクレターゼ1)遺伝子の転写を抑制することでAβ産生の源流であるAPP切断を減少させることが示されています。さらにリチウムはγ-セクレターゼ活性も低下させることでAPPからのAβ生成を抑制しうることが報告されており、Aβプラーク形成の阻止につながる多面的作用を持ちます。以上のように、GSK-3β経路の制御を通じてタウ病理とアミロイド病理の双方に働きかける点が、リチウムの神経変性抑制作用の中核と考えられています。
もう一つ重要な作用は神経炎症の抑制です。ADを含む認知症では慢性的な炎症反応やグリア細胞の活性化が神経細胞死を増幅する要因となりますが、リチウムには抗炎症作用があることが知られています。具体的には、リチウムは炎症関連転写因子NF-κBやSTAT3の活性を阻害し、過剰なサイトカイン産生を抑えることで神経炎症を緩和します。この作用はGSK-3β阻害とも関連しており、リチウムが炎症誘導経路を遮断するメカニズムの一部と考えられます。実験モデルでは、リチウム投与により脳内のミクログリアやアストロサイトの過剰な活性化が抑えられ、炎症性サイトカイン(IL-1βやTNF-αなど)の発現低下や抗炎症性サイトカイン(IL-10など)の増加が報告されています。これらの結果は、リチウムが神経炎症のダメージを軽減し神経保護的な環境を醸成することを示唆します。
加えて、リチウムは神経栄養・生存経路を賦活する作用も持ちます。脳由来神経栄養因子(BDNF)の産生誘導やシナプス可塑性の増強、海馬神経新生の促進など、神経細胞ネットワークの維持改善に寄与する効果が報告されています。リチウム投与はBDNF遺伝子の転写を促進することでシナプス形成や神経細胞の耐久性を高め、長期的には脳の認知予備能を向上させる可能性があります。また、ミトコンドリア機能の維持や酸化ストレス軽減、オートファジー促進による不要なタンパク質凝集体の処理促進など、細胞レベルでの保護効果も認められています。こうしたマルチターゲットな作用メカニズムにより、リチウムはAD病理の進行に伴う様々な有害事象を同時に抑制できる可能性があります。事実、プレクリニカル研究(細胞・動物モデル)ではリチウム投与によりアミロイド斑とタウ病変の減少、神経細胞死の抑制、認知機能の改善が繰り返し示されています。臨床研究で得られたバイオマーカー改善効果(Aβ42上昇やタウリン酸化抑制)も、これら基礎的作用がヒトでも発現していることを裏付けている可能性があります。
結論
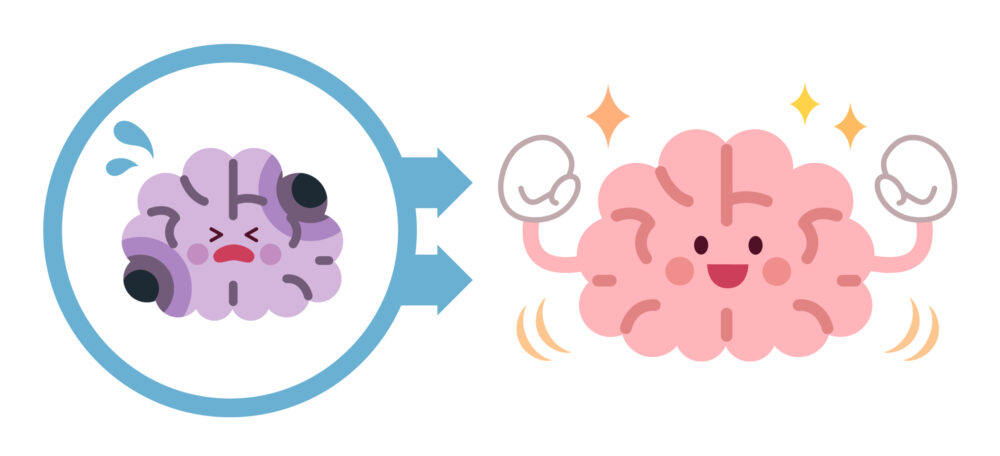
炭酸リチウムの認知症予防効果について、疫学的には双極性障害患者や地域集団でリチウム曝露と認知症リスク低下の関連が示唆され、臨床研究では小規模ながら認知機能低下の抑制効果と病理マーカー改善が報告されています。こうしたエビデンスは、リチウムが疾患修飾的な作用を持ちうる可能性を支持するものです。その作用機序として、GSK-3β阻害を起点とするタウ病変・アミロイド病変の抑制や神経炎症の軽減といった多面的な神経保護効果が解明されつつあります。現時点でリチウムは認知症治療の正式な適応ではありませんが、将来的には高リスク群に対する低用量リチウムの予防的投与が、新たな認知症予防戦略として位置付けられる可能性があります。その実現には、大規模介入研究による有効性と安全性の確立が不可欠であり、特に高齢者への長期投与に伴うリスク管理や最適用量の検討など解決すべき課題も残されています。しかし、現在得られている知見は十分に有望であり、炭酸リチウムという古典的薬剤が認知症の予防・進行抑制に役立つ可能性が改めて注目されています。今後さらなる研究の蓄積により、リチウム療法が認知症領域で果たしうる役割が一層明らかになるでしょう。各種のエビデンスを統合的に評価しながら、既存薬のリポジショニングによる認知症予防という観点で炭酸リチウムの価値を再検討していく必要があります。
参考文献