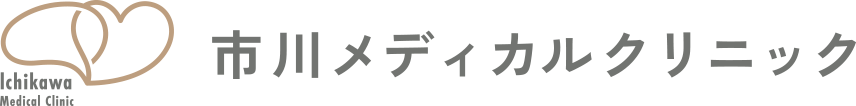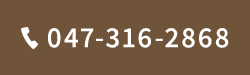人前に出ると緊張してしまう~それは社交不安症かもしれません
社交不安症(SAD)とは?
「人前に出ると緊張してしまう」「初対面の人と話すのが怖い」
そんな風に強く感じて人前でうまく話せなくなってしまったり、そういう場面を避けてしまうことってありませんか?もしかするとそれは、「社交不安症」のサインかもしれません。
「社交不安症」は、「人前で注目を浴びる状況で極度の不安を感じ、行動を回避してしまう」精神疾患です。
生涯有病率(一生のうちに一度でも社交不安症を経験する割合)は13%で、7人に一人が一生のうちにこの障害にかかる可能性があるとされています。
当クリニックにも同じような悩みを抱える方が多くいらっしゃっています。
このブログでは、Aさんのケースを例に社交不安症について詳しく説明していきます。
環境や社会的役割の変化がきっかけとなることも
Aさん(仮名)は、新卒として会社に入り、仕事に前向きに取り組んでいました。しかし、初めての社内プレゼンテーションをすることになりました。大勢の社員の前で話すという役割を与えられ、その日が近づくにつれて、これまで感じたことのない強い不安に襲われるようになったのです。
実はAさんは、高校時代から特に意識していたわけではなかったのですが、人前に出ることを避けてきました。ただ、その頃はまだ大きな問題にはなっていませんでした。
Aさんのように、社会人や大学進学という環境や社会的役割の変化によって、人前で強い不安や緊張を自覚するようになることはとても多いです。
社交不安症とは?~どんな症状が出るのか
プレゼンテーションの日が近づくにつれ、「もし、うまく説明できなかったらどうしよう」「質問に答えられなかったら恥ずかしい」「みんなに呆れられたら…」次々とネガティブな想像が頭の中を駆け巡り、夜もなかなか寝付けない日が続きました。不安と焦燥感で心臓がドキドキして、手のひらにじっとりと汗がにじむこともありました。
プレゼン当日も、Aさんの体は強張り、壇上に立つと、声や体が震え頭は真っ白になりました。数分のプレゼンを終えたものの、内容はほとんど覚えていませんでした。質疑応答もままならず、プレゼン後は深い疲労感と自己嫌悪に襲われました。そして、翌朝から会社に行くことができなくなってしまったのです。
そして、受診した医療機関で「社交不安症」と診断されました。
社交不安症とは、特定の社会的な状況や人前での行動に対して、過度な不安や恐怖を感じ、日常生活に支障をきたす精神疾患の一つです。
主な症状
社交不安症の症状は、以下のようなものがあります。
精神症状: 強い緊張感、失敗への恐怖、対人回避等
・人前で注目される状況を過度に恐れる。
・他人にどう思われているか気にしすぎる。
・失敗して恥をかくのではないかと過度に心配する。
・社交的な場面を避ける。
身体症状: 赤面、発汗、動悸、震え等
・顔が赤くなる。
・冷や汗をかく。
・心臓がドキドキする。
・手が震える。
・息苦しくなる。
・めまいを感じる。
発症の原因とは?~過去の出来事が関係していることも
社交不安症は、遺伝や育ってきた環境や経験など、様々な要因が複雑に絡み合って起こると考えられています。
- 遺伝: 家族に社交不安症の人がいる場合、遺伝的な要因で発症しやすい傾向があります。
- 環境要因: 子供の頃の恥ずかしい経験、叱責、いじめ、家庭環境などがリスクを高めることがあります。
これらの要因が重なり、社交不安症が発症すると考えられています。
これまで高校時代から人前に立つ状況を無意識的に避けてきたAさんにとって、社会人になり初めて直面したプレゼンテーションという場面で、抑えられていた不安が一気に表面化したことが考えられます。
過去の恥ずかしい体験や、子供の頃に大勢の前で叱責された経験といった記憶は、その後の社会生活における不安の種となり、特定の状況で強い緊張を引き起こすことがあります。Aさんの場合、発症当初は明確な記憶として思い出すことはなかったですが、治療による振り返りの中で、中学時代に大勢の前で叱責された経験が心の奥底に影響を与えていたことが明らかになってきました。
高校時代までは、人前に立つ状況を避けることで何とかやり過ごせてきたAさんにとって、社会人になり、避けることが難しい状況に直面したことが、自身の抱える不安と向き合うきっかけとなったのです。
社交不安症の治療
社交不安症の治療は第一選択は認知行動療法 (CBT) です。メタ解析では、治療終了時の効果量 g = 0.74 と報告されています。薬物療法としては SSRI(例:パロキセチン、セルトラリン)が推奨されています。当院ではカウンセラーが在籍し、薬物療法との併用も可能です。
Aさんの場合は、薬物療法と認知行動療法、過去の経験による心の傷に向き合うための心理療法が提案されました。薬物療法によって、Aさんの過度な不安は少しずつ和らいでいきました。認知行動療法では、不安を感じる状況に対する考え方について振り返り、修正したり、段階的に苦手な状況に慣れていく練習をしたりしました。カウンセリングを通して、Aさんは過去の漠然とした不安の根源に気づき、それが現在の対人関係や自信のなさに繋がっていたことを理解していきました。
治療が進むにつれて、Aさんの中で少しずつ変化が起こり、少人数の会議でなら、緊張しながらも自分の意見を言えるようになったり、プレゼンでも徐々に落ち着いて話せるようになっていきました。そうした経験を重ねる中で、「また失敗するかもしれない」という予期不安が軽減していきました。
「もしかしたら…」と感じたら
もし、Aさんのように人前に出ることに強い不安や緊張を感じ、日常生活に支障が出ている場合は、医療機関に相談してみてもいいかもしれません。そして、過去の経験が今の苦しみに繋がっていると感じるなら、それは決して個人的な弱さではありません。
過去の出来事は、時に心の深い部分に影響を与え、現在の不安として現れることがあります。
当クリニックでは、薬物といった社交不安症の治療に加え、必要に応じてカウンセリングもご案内しております。
一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 社交不安症を放置するとどうなりますか?
放置すると慢性化しやすく、学校・仕事・人間関係で「避ける―失敗―自己評価低下」の悪循環が続きます。未治療のまま10年以上持続するケースが約半数に上り、うつ病・アルコール依存・ひきこもりの合併率が高まると報告されています。早期介入が生活の質と社会機能を守る鍵です。
Q2. 薬だけで治りますか?
SSRI や SNRI は身体症状(動悸・発汗など)と予期不安の軽減に有効ですが、服薬中断後に再発するリスクも30〜50 % と示されています。CBTを併用 すると寛解率が大幅に向上し、12 か月以上のフォローアップでも効果が持続します(効果量 g = 0.74)。薬物療法単独より併用または CBT 単独 の方が長期転帰は良好です。
Q3. 治療期間はどのくらい?
薬物療法:効果発現まで 4〜6 週、再発防止のため 少なくとも 6〜12 か月 の継続が推奨されます。
CBT:週1回・50分×12〜16 セッションが標準で、終了後もホームワークを続けると再発率が低下します。
個々の症状と生活環境により延長することもありますが、3〜4 か月で不安スコアが半減する例が多いです。
Q4. 「SAD とは違う不安症かも?」と思ったら?
社交不安症と似た症状を呈する疾患には 全般不安症(GAD)・パニック症・特定の恐怖症・強迫症・自閉スペクトラム症・回避性パーソナリティ障害 などがあります。自己判断は難しいため、精神科専門医 に相談し評価を受けましょう。
引用:日本不安症学会の診療ガイドライン https://www.jsnp-org.jp/news/img/20210510.pdf